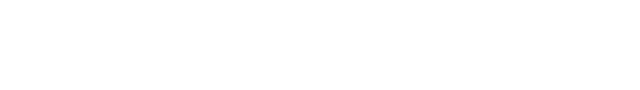決めつけられるという不本意
コロナを例に…。
コロナが世に出てきた当初、「コロナが怖い」で思い浮かぶ対象は「感染」でした。確かに今春の緊急事態宣言前はそのようでした。しかし実際に緊急事態宣言に入り、人々の往来が少なくなると、「コロナが怖い」は、「仕事がなくなるのが怖い」「存在価値がなくなるようで怖い」「四六時中家族と一緒にいるのが怖い」など怖さの対象が散らばりました。この時期になっても「コロナが怖い」を当初のように「感染が怖い」と決めつけていたら、話し手は「わかってもらえない」と孤独感を覚えたでしょう。
ボランティアでも生じる誤解
このような事例は、私自身も東日本大震災後の援助に出向いて気づかされました。
この時もコロナの当初と同じで、被災直後に誤解は生じません。当初は撤去や物資援助など助けてほしいことが「目に見える (visible)」 ため、被災者と援助者との間にズレは生じないのです。しかし被災者が仮設住宅に移り、「被災者の心のケア」にシフトしたころより、様々な誤解が生じてきます。
ここで熱意あるボランティアほど、被災者に明るく、または寄り添うように声をかけようとします。しかしこの時期になると、被災者と援助者が同じ熱量ではいられません。実際にお知らせや催し物のPRなどを一軒一軒まわっても、玄関に出てこないことも多いのです。ボランティア側は、「傷ついているから、まだ温まらないのは仕方ない」などと考えがちですが、そうではありません。明らかに援助者側が、勝手に崇高な目標を掲げ、プッシュすることがボランティア精神というような観念に先走っているのです。
もっといえば「せっかく援助に来たのだから、ありがとうといってもらいたい」という想いもあるでしょう。しかし人の感情を適切に見積もらないと、結果的に先走って相手に届きません。しかも困ったことにこのような熱意は、世間的に見れば一見間違ってもいないし、批判されることでもありません。従って援助者側が自分達の手助け方がどうだったか真摯に振り返る機会がなく、また同じような支援が繰り返される場合もあります。
家庭こそ「決めつけないで訊いていく」場へ
コロナ禍・被災地支援と例を出しましたが、まさに援助の場で生じるのが「決めつけ」です。従ってそもそも援助で成り立っている家庭という場は、ことさら「すり合わせを必要とする場」と思います。ただでさえ日本語は省略が多く、また文化としても「言わなくてもわかる人」が美徳という価値観が日本にはあります。読むことばかりに価値観を置き、訊かずにすり合わせないことで、悶々としたものを引きずる危険性を家庭ははらんでいます。
「どのようなことで悩んでますか?」。近しい関係ほど、日頃のすり合わせが肝心です。