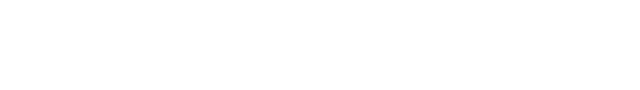主治医制の意義
精神科の診察室では、言葉を交わすことで、患者さんの中に少しずつ「考え方の地図」が形づくられていきます。それは単なるアドバイスではなく、繰り返しのやりとりの中で体に馴染んでいく言葉です。
「雲行きが悪くない」「波風が立たない」「軋轢がない」「先細りしない」「見境いがついている」「折り合いはやゆ良い」――患者さんが発して来るようになるこういった表現は、診察室での活きた言葉のやりとりの中で、患者さん自身が少しずつ覚え、使いこなしていくようになります。
これらはマニュアルには載らない、柔らかく抽象的な比喩ですが、だからこそ、自分の気持ちや出来事を、以前より距離を置いて眺めている証しになっています。言葉数が増えていくことは人間関係において武器になります。そのように多彩な言葉を使えるようになることで、日常の中でも余裕が生まれ、他者とのやりとりに巻き込まれることが少なく、従って必要のないぶつかりも避け、程よく受け止めたり、あるいはいなせるようになっていきます。
この「距離の取り方」を身につけることこそ、精神科診療の中核と考えています。単に症状を聞き、薬を出し、それを診察室外で試して以後結果を確認する、いわゆる内科などでは当たり前の方針では、このような深い変化は起きません。もちろん内科では科学に基づいていますから、その分個人事情や背景を問いません。一方で精神医療では、診察室の中で実際に経験された言葉や気づきが、その人の生活にそのまま持ち帰られていく。この過程にこそ意味があります。
だからこそ、回数を重ねて縦断的に診ていく主治医制が、精神医療では大切であると思います。医師との関係性の中で、次第に自分の“内側の気候”に目を向けていくこと。それが、急な変化に押し流されず、脆さを見せずに生きていく力につながるのだと思っています。